不妊治療における先進医療について、費用や効果、リスク、そして治療の流れまでを網羅的に解説します。
体外受精、顕微授精、胚移植といった具体的な治療法ごとに、それぞれの特徴やメリット・デメリットを分かりやすく比較することで、ご自身に最適な治療法を見つけるための判断材料を提供します。
助成金制度についても触れているので、費用の負担軽減についても理解を深めることができます。
さらに、先進医療以外の選択肢や、治療を受ける上での心構え、よくある質問など、不妊治療に関する様々な情報を網羅しています。
この記事を通して、より informed な意思決定をし、希望に満ちた未来へと繋がる一歩を踏み出しましょう。
1. 不妊治療の先進医療とは?
不妊治療の先進医療とは、厚生労働省が認可した先進的な医療技術を用いた不妊治療のことです。
一般的に行われている不妊治療よりも高度な技術や設備が必要となる場合が多く、治療費が高額になる傾向があります。
しかし、妊娠の可能性を高めるために、積極的に先進医療を選択する夫婦も少なくありません。
1.1 先進医療と高度生殖医療の違い
「先進医療」と「高度生殖医療」は混同されがちですが、明確な違いがあります。
高度生殖医療は、体外受精や顕微授精といった生殖補助医療全体を指す言葉です。
一方、先進医療は、高度生殖医療の中でも特に先進的な技術を用いた治療法で、厚生労働省が認可したもののみが該当します。
つまり、先進医療は高度生殖医療の一部と言えるでしょう。
1.2 先進医療の対象となる治療法
現在、日本で先進医療の対象となっている主な不妊治療法は以下の通りです。
1.2.1 体外受精
体外受精は、女性の卵巣から採取した卵子と、男性から採取した精子を体外で受精させる治療法です。
受精卵を子宮に戻すことで妊娠を目指します。
体外受精は、卵管が閉塞している場合や男性不妊の場合などに有効な治療法です。
1.2.2 顕微授精
顕微授精は、体外受精の一種で、顕微鏡下で1つの精子を卵子に直接注入する治療法です。
重度の男性不妊の場合に有効とされています。
1.2.3 胚移植
胚移植は、体外受精や顕微授精で得られた受精卵(胚)を子宮内に戻す治療法です。
胚移植の技術も進歩しており、良好な胚を選択して移植することで妊娠率の向上に繋がっています。
| 治療法 | 概要 | 適応 |
|---|---|---|
| 体外受精 | 体外で卵子と精子を受精させる | 卵管閉塞、男性不妊など |
| 顕微授精 | 精子を卵子に直接注入する | 重度の男性不妊 |
| 胚移植 | 受精卵を子宮内に戻す | 体外受精、顕微授精後 |
2. 不妊治療の先進医療とは?
不妊治療の先進医療とは、厚生労働省が認可した先進的な医療技術を用いた不妊治療のことを指します。
一般的に行われている不妊治療よりも高度な技術や設備が必要となる場合が多く、治療効果の向上や新たな治療の可能性が期待されています。
しかし、先進医療は保険適用外となるため、費用が高額になる傾向があります。
治療を受ける際には、費用面だけでなく、効果やリスクについても十分に理解しておくことが重要です。
2.1 先進医療と高度生殖医療の違い
不妊治療において、「先進医療」と「高度生殖医療」という言葉は混同されがちですが、明確な違いがあります。
高度生殖医療は、体外受精や顕微授精といった生殖補助医療(ART)全体を指す言葉です。
一方、先進医療は、高度生殖医療の中でも特に先進的な技術を用いた治療法で、厚生労働省によって認可されたもののみを指します。
つまり、先進医療は高度生殖医療の一部ということになります。
簡単に言うと、高度生殖医療という大きな枠組みの中に、先進医療という特別なカテゴリーが存在するイメージです。
高度生殖医療全てが先進医療というわけではありません。
| 項目 | 高度生殖医療 | 先進医療 |
|---|---|---|
| 定義 | 体外受精や顕微授精などの生殖補助医療全般 | 高度生殖医療の中でも特に先進的な技術を用いた治療で、厚生労働省が認可したもの |
| 保険適用 | 一部適用外 | 適用外 |
| 費用 | 治療法によって異なる | 高額になる傾向 |
2.2 先進医療の対象となる治療法
先進医療の対象となる治療法は、時代とともに変化し、新たな技術が追加されたり、既存の技術が除外されたりすることがあります。
常に最新の情報を厚生労働省のウェブサイトなどで確認することが大切です。
代表的な治療法としては、以下のようなものがあります。
2.2.1 体外受精
体外受精は、女性の卵子と男性の精子を体外で受精させ、受精卵を子宮に戻す治療法です。
排卵誘発剤を用いて複数の卵子を採取し、体外で受精させることで、妊娠の可能性を高めることを目指します。
体外受精は、卵管が閉塞している場合や、男性の精子数が少ない場合などに有効な治療法です。
2.2.2 顕微授精
顕微授精は、体外受精の一種で、細いガラス針を用いて精子を卵子に直接注入する治療法です。
男性の精子数が極端に少ない場合や、精子の運動率が低い場合などに有効な治療法です。
顕微授精は、体外受精よりもさらに高度な技術を要するため、費用も高額になる傾向があります。
顕微授精は、重度の男性不妊に悩むカップルにとって大きな希望となる治療法です。
しかし、自然妊娠に比べて染色体異常のリスクがわずかに高いという報告もあるため、医師とよく相談することが重要です。
2.2.3 胚移植
胚移植は、体外受精や顕微授精で得られた受精卵(胚)を子宮内に戻す治療法です。
胚移植は、体外受精や顕微授精の最終段階であり、妊娠成立のために重要なステップです。
胚移植の成功率は、女性の年齢や子宮の状態、胚の質など様々な要因に影響されます。
胚移植は、体外受精や顕微授精と合わせて行われる治療法であり、単独で行われることはありません。
移植する胚の数を増やすことで妊娠率は上がりますが、多胎妊娠のリスクも高まるため、医師とよく相談して決める必要があります。
3. 不妊治療の先進医療の種類と費用
不妊治療における先進医療とは、厚生労働大臣が認可した先進的な医療技術を用いた治療法のことです。
一般的に行われている不妊治療とは異なり、公的医療保険は適用されませんが、治療費の一部を助成する制度があります。
体外受精や顕微授精といった高度な技術を用いることで、妊娠の可能性を高めることを目指します。
3.1 体外受精の費用
体外受精は、卵子と精子を体外で受精させ、受精卵を子宮に戻す治療法です。
費用は医療機関によって異なりますが、一般的には1回あたり30万円から50万円程度です。
この費用には、卵巣刺激のための注射や採卵、培養、移植などの費用が含まれます。
また、顕微授精を追加で行う場合は、さらに費用が加算される場合があります。
体外受精の費用は、使用する薬剤の種類や量、培養期間などによって変動するため、事前に医療機関で詳細な説明を受けることが重要です。
3.2 顕微授精の費用
顕微授精は、顕微鏡を用いて精子を卵子に直接注入する治療法です。
男性不妊の場合や、体外受精で受精がうまくいかない場合に用いられます。
費用は体外受精とほぼ同じで、1回あたり30万円から50万円程度です。
体外受精と同時に行う場合は、追加費用として5万円から10万円程度かかることが多いです。
顕微授精は、高度な技術と設備を必要とするため、費用が高額になる傾向があります。
治療を受ける前に、費用についてしっかりと確認しておきましょう。
3.3 胚移植の費用
胚移植は、体外受精や顕微授精で得られた受精卵(胚)を子宮内に戻す治療法です。
費用は、体外受精や顕微授精に含まれている場合と、別途費用がかかる場合があります。
別途費用がかかる場合は、1回あたり5万円から10万円程度が相場です。
また、凍結保存していた胚を移植する場合は、凍結保存費用や融解費用が別途発生します。
胚移植の費用は、新鮮胚移植か凍結胚移植かによっても異なるため、事前に確認が必要です。
3.4 助成金制度について
不妊治療は高額な費用がかかるため、国や地方自治体では助成金制度を設けています。
助成金の対象となる治療法や助成額、申請方法などは、各自治体によって異なります。
申請には、医療機関の診断書や収入証明書などが必要となる場合が多いです。
| 助成の種類 | 内容 |
|---|---|
| 特定不妊治療助成事業 | 体外受精や顕微授精などの特定不妊治療に対し、費用の一部を助成する制度です。 |
| 一般不妊治療助成事業 | タイミング法や人工授精などの一般不妊治療に対し、費用の一部を助成する制度です。自治体によっては、特定不妊治療と合わせて助成を受けられる場合があります。 |
助成金制度を利用することで、経済的な負担を軽減できる可能性があります。
お住まいの自治体の助成制度について、詳しく調べてみましょう。
4. 不妊治療の先進医療の効果とリスク
不妊治療の先進医療には、体外受精、顕微授精、胚移植などがあり、それぞれに効果とリスクが存在します。
治療を受ける前に、それぞれのメリット・デメリットを理解し、ご自身に合った治療法を選択することが重要です。
4.1 体外受精の効果とリスク
体外受精は、卵巣から採取した卵子と精子を体外で受精させ、受精卵を子宮に戻す治療法です。
自然妊娠が難しい場合でも妊娠の可能性を高めることができます。
4.1.1 多胎妊娠のリスク
体外受精では、一度に複数の受精卵を子宮に戻すことがあります。
そのため、双子や三つ子などの多胎妊娠のリスクが高まります。多胎妊娠は母体と胎児への負担が大きいため、注意が必要です。
4.1.2 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)
体外受精では、排卵誘発剤を使用するため、卵巣過剰刺激症候群(OHSS)を発症する可能性があります。
OHSSは、卵巣が腫れ、腹痛や吐き気などの症状が現れる病気です。重症化すると入院が必要になる場合もあります。
4.2 顕微授精の効果とリスク
顕微授精は、顕微鏡下で1つの精子を卵子に直接注入する治療法です。男性不妊の場合に有効な治療法です。
体外受精と同様に、妊娠の可能性を高めることができます。
4.2.1 染色体異常のリスク
顕微授精では、自然な受精とは異なるため、まれに染色体異常のリスクがわずかに上昇する可能性が示唆されています。
ただし、そのリスクは非常に低いとされています。
4.3 胚移植の効果とリスク
胚移植は、体外受精や顕微授精で得られた受精卵(胚)を子宮内に戻す治療法です。
胚移植の成功は、妊娠成立の鍵となります。
4.3.1 着床率
胚移植の着床率は、女性の年齢や胚の質、子宮の状態などによって異なります。
若い女性ほど着床率は高く、高齢になるにつれて低下する傾向があります。
4.3.2 流産のリスク
胚移植後、妊娠が成立しても、流産のリスクは存在します。
流産は、染色体異常や子宮の異常、母体の健康状態など様々な要因が考えられます。
| 治療法 | 効果 | リスク |
|---|---|---|
| 体外受精 | 自然妊娠が難しい場合でも妊娠の可能性を高める | 多胎妊娠、卵巣過剰刺激症候群(OHSS) |
| 顕微授精 | 男性不妊の場合に有効 | 染色体異常のリスク(低い) |
| 胚移植 | 妊娠成立の鍵となる | 着床率の変動、流産のリスク |
これらの情報に加えて、医師との相談を通じて、ご自身の状況に最適な治療法を選択することが大切です。
治療のメリットだけでなく、リスクについても十分に理解し、納得した上で治療に臨みましょう。
5. 不妊治療の先進医療を受けるまでの流れ
不妊治療の先進医療を検討し始めると、様々な情報が溢れていて戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか。
ここでは、治療を受けるまでの一般的な流れをステップごとにご説明します。
スムーズに治療を始められるよう、ぜひ参考にしてみてください。
5.1 医療機関の選び方
自分に合った医療機関を選ぶことは、治療の成功に大きく関わってきます。
様々な要素を考慮しながら様々な要素を考慮しながら、じっくりと検討することが大切です。
| ポイント | 詳細 |
|---|---|
| 専門性 | 体外受精や顕微授精などの実績が豊富であるか、特定の不妊治療に特化しているかなどを確認しましょう。日本生殖医学会のウェブサイトなどで、認定医や専門医の情報も調べることができます。 |
| 通いやすさ | 治療は長期間に及ぶ可能性もあるため、自宅や職場から通いやすい場所にあるかどうかも重要なポイントです。 |
| 設備 | 最新の医療設備が整っているか、培養室の環境などが適切に管理されているかなども確認しておきましょう。 |
| サポート体制 | 不妊治療は精神的な負担も大きいため、カウンセリング体制が充実しているか、看護師やスタッフの対応は丁寧かなども確認しておくと安心です。 |
複数の医療機関を比較検討し、説明会やカウンセリングに積極的に参加してみるのも良いでしょう。
最終的には、ご自身で納得できる医療機関を選ぶことが大切です。
5.2 初診から治療開始まで
医療機関が決まったら、いよいよ初診です。
初診から治療開始までは、一般的に以下のような流れになります。
- 問診・検査問診・検査:現在の状況や既往歴、月経周期などについて問診を受け、血液検査や超音波検査などを行います。ご夫婦で受診し、精液検査を行う場合もあります。
- 検査結果の説明・治療方針の決定検査結果の説明・治療方針の決定:検査結果に基づいて、医師から今後の治療方針について説明を受けます。疑問点や不安なことは、この際にしっかりと相談しましょう。
- 治療開始治療開始:治療方針に同意したら、いよいよ治療開始となります。体外受精や顕微授精などの先進医療を受ける場合は、所定の手続きが必要になります。
5.2.1 治療開始までの期間
初診から治療開始までの期間は、医療機関の混雑状況や検査結果、治療内容によって異なります。
数週間から数ヶ月かかる場合もあるので、余裕を持ってスケジュールを立てましょう。
5.3 治療期間の目安
先進医療を含む不妊治療の期間は、患者さんの状態や治療法によって大きく異なります。
体外受精や顕微授精の場合、採卵から胚移植まで約2週間から1ヶ月程度かかります。
また、一度の治療で妊娠に至らない場合、複数回の治療が必要となることもあります。
治療期間については、医師とよく相談し、ご自身の状況に合わせた計画を立てるご自身の状況に合わせた計画を立てることが大切です。
6. 不妊治療の先進医療を受ける際の注意点
不妊治療の先進医療を受けるにあたっては、いくつかの注意点があります。
治療の成功のためにも、そしてご自身の心身の健康のためにも、事前にしっかりと理解しておくことが大切です。
6.1 年齢制限
先進医療の中には、年齢制限が設けられている治療法があります。
これは、女性の加齢に伴い妊娠率が低下すること、また合併症のリスクが高まることなどを考慮したものです。
年齢制限は治療法によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
6.2 治療を受ける上での心構え
不妊治療は、身体的にも精神的にも負担がかかることがあります。
治療期間の長さや結果の不確実性など、様々な不安やストレスを感じることもあるでしょう。
パートナーとの協力、医療スタッフとの良好なコミュニケーション、そしてご自身の心身の健康管理が重要です。
6.2.1 治療の長期化への覚悟
不妊治療は、必ずしもすぐに結果が出るものではありません。
治療が長期化する可能性もあることを理解し、焦らずに治療に取り組む心構えが必要です。
治療期間中は、定期的な通院が必要となります。仕事や日常生活との両立が難しい場合もあるため、事前にスケジュール調整や周囲の理解を得ておくことが大切です。
6.2.2 精神的な負担への対処
治療の過程で、精神的な負担を感じることは少なくありません。
治療の結果に対する不安やプレッシャー、ホルモンバランスの変化による情緒不安定など、様々な要因が考えられます。
信頼できる人に相談したり、カウンセリングを受けるなど、ご自身に合った方法でストレスを軽減していくことが大切です。
6.2.3 パートナーとの連携
不妊治療は、夫婦二人三脚で取り組むものです。
治療方針や今後の計画について、パートナーとよく話し合い、共通の認識を持つことが重要です。
お互いを支え合い、協力して治療を進めていくことが、成功への近道となります。
6.3 セカンドオピニオンの重要性
先進医療を受けるかどうか、どの治療法を選択するかは、人生における大きな決断です。
一つの医療機関の意見だけでなく、他の医療機関の意見も聞くことで、より多角的な視点から治療法を検討することができます。
セカンドオピニオンを受けることで、納得のいく治療法を選択し、安心して治療に臨むことができるでしょう。
| 注意点 | 詳細 |
|---|---|
| 年齢制限 | 治療法によって年齢制限が異なるため、事前に確認が必要。 |
| 治療の長期化 | 治療が長期化する可能性があることを理解し、焦らず治療に取り組む。仕事や日常生活との両立も考慮する。 |
| 精神的な負担 | 治療の結果への不安やプレッシャー、ホルモンバランスの変化による情緒不安定などへの対処法を検討する。信頼できる人に相談したり、カウンセリングを受けるのも有効。 |
| パートナーとの連携 | 治療方針や今後の計画について、パートナーとよく話し合い、共通の認識を持つ。 |
| セカンドオピニオン | 他の医療機関の意見も聞くことで、より多角的な視点から治療法を検討し、納得のいく選択をする。 |
これらの注意点を踏まえ、ご自身にとって最適な治療法を選択し、前向きに治療に取り組んでいきましょう。
7. 先進医療以外の不妊治療
先進医療は高度な技術を用いた不妊治療ですが、その他にも様々な治療法があります。
それぞれの治療法の特徴を理解し、ご自身に合った治療法を選択することが重要です。
ここでは、代表的な先進医療以外の不妊治療について解説します。
7.1 タイミング法
タイミング法は、自然妊娠を促すための基本的な不妊治療です。
排卵日を予測し、その時期に合わせて性交渉を持つことで妊娠の確率を高めます。
基礎体温の測定や、排卵日予測キット、超音波検査などを用いて排卵日を特定します。
体に負担が少ない治療法であることが大きなメリットです。他の治療と比べて費用も抑えられます。
7.2 人工授精
人工授精は、精液を採取し、洗浄・濃縮処理を行った後、カテーテルを用いて子宮内に直接注入する治療法です。
タイミング法で妊娠に至らなかった場合や、男性側に軽度の不妊原因がある場合に有効とされています。
体外受精に比べると費用が抑えられるというメリットがあります。また、体外受精ほど体に負担がかかりません。
7.3 一般不妊治療と先進医療の併用
場合によっては、一般不妊治療と先進医療を併用することもあります。
例えば、タイミング法や人工授精である程度の期間妊娠に至らなかった場合、体外受精や顕微授精などの先進医療にステップアップすることが考えられます。
また、先進医療を行う際に、排卵誘発剤を使用して卵胞の成長を促すこともあります。
これは一般不妊治療で行われる方法と同様です。それぞれの治療法の特徴を理解し、医師と相談しながら最適な治療計画を立てることが重要です。
| 治療法 | 概要 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| タイミング法 | 排卵日に合わせて性交渉を行う | 体に負担が少ない、費用が安い | 妊娠率が低い |
| 人工授精 | 精子を子宮内に直接注入する | 体外受精より負担が少ない、費用が安い | タイミング法より妊娠率は高いが、体外受精よりは低い |
どの治療法を選択するかは、年齢、不妊の原因、治療期間、費用などを考慮して決定する必要があります。
医師とよく相談し、ご自身に合った治療法を見つけることが大切です。
また、治療を受ける際には、精神的な負担も大きいため、パートナーや家族のサポートも重要となります。
8. あなたに合った不妊治療の先進医療の選び方
不妊治療の先進医療は、様々な種類があり、それぞれに特徴があります。
どの治療法が自分に合っているのか、悩まれる方も多いでしょう。
費用や効果、リスクなどを考慮しながら、ご自身にとって最適な治療法を選択することが大切です。
8.1 費用と効果のバランス
先進医療は保険適用外のため、治療費が高額になる場合があります。
治療にかかる費用と、その治療によって期待できる効果のバランスをしっかりと見極める必要があります。
体外受精や顕微授精といった治療法は、妊娠率を高める効果が期待できますが、費用も高額になりがちです。
ご自身の経済状況も考慮しながら、無理なく続けられる治療法を選びましょう。
8.2 リスクへの理解
先進医療には、それぞれ特有のリスクが存在します。
例えば、体外受精では多胎妊娠や卵巣過剰刺激症候群(OHSS)のリスクがあり、顕微授精では染色体異常のリスクが指摘されています。
また、胚移植では着床しない可能性や流産のリスクも考慮しなければなりません。
これらのリスクについて十分に理解し、納得した上で治療を受けることが重要です。
| 治療法 | 主なリスク |
|---|---|
| 体外受精 | 多胎妊娠、卵巣過剰刺激症候群(OHSS) |
| 顕微授精 | 染色体異常 |
| 胚移植 | 着床率、流産 |
8.3 医師との相談
どの治療法が最適かは、あなたの年齢、不妊の原因、過去の治療歴、そしてご夫婦の価値観などによって異なります。
担当医とじっくり話し合い、それぞれの治療法のメリット・デメリットを理解した上で、最終的にどの治療法を選択するかを決定しましょう。
セカンドオピニオンを求めることも有効な手段です。
疑問や不安を解消し、納得のいく治療を受けるために、医師とのコミュニケーションを大切にしましょう。
体外受精、顕微授精、胚移植といった先進医療は、それぞれに異なる特徴や費用、効果、リスクがあります。
ご自身の状況や希望に合わせて、最適な治療法を選択することが大切です。
医師との綿密な相談を通じて、納得のいく治療を受けてください。
9. 不妊治療の先進医療に関するよくある質問
不妊治療に関する先進医療について、よくある質問にお答えします。
9.1 先進医療の保険適用について
先進医療は、公的医療保険が適用されない自由診療です。
ただし、先進医療にかかる費用の一部を助成する制度があります。
自治体によって助成内容が異なるため、お住まいの自治体にご確認ください。
9.2 治療期間中の生活について
治療期間中は、規則正しい生活を心がけ、バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠をとりましょう。
また、ストレスをためないように、リラックスできる時間を作ることも大切です。
飲酒や喫煙は控えるようにしてください。
仕事との両立については、治療内容やスケジュールによって異なります。
通院の頻度や治療による身体への負担などを考慮し、必要に応じて職場に相談しましょう。
9.3 妊娠後のサポート体制
先進医療で妊娠した場合、妊娠初期から出産まで、一般的な妊婦健診と同様のサポートを受けることができます。
分娩は、提携している産科医療機関で行うことになります。
妊娠中の不安や疑問については、医療機関に相談しましょう。
9.4 治療の成功率について
先進医療の成功率は、年齢、治療内容、原因となる不妊の状態などによって異なります。
また、同じ治療法でも医療機関によって差がある場合があります。
治療を受ける前に、医師から十分な説明を受け、ご自身の状況に合わせた成功率について理解しておきましょう。
9.5 その他、患者様からよくいただくご質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 先進医療を受ける際の年齢制限はありますか? | 医療機関によって異なりますが、一般的には40代前半までを目安としていることが多いです。詳しくは、各医療機関にお問い合わせください。 |
| 先進医療は、他の不妊治療と併用できますか? | 場合によっては併用可能です。例えば、タイミング法や人工授精と併用して行うこともあります。医師と相談の上、最適な治療法を選択しましょう。 |
| 治療中に、何か副作用はありますか? | 治療内容によっては、卵巣過剰刺激症候群(OHSS)や多胎妊娠などのリスクがあります。医師から副作用についての説明を受け、十分に理解した上で治療を受けるようにしましょう。 |
| セカンドオピニオンを受けることはできますか? | セカンドオピニオンを受けることは可能です。他の医療機関の医師の意見を聞くことで、治療方針の再確認や新たな選択肢の発見につながる可能性があります。 |
| 治療費の支払方法にはどのようなものがありますか? | 医療機関によって異なりますが、現金、クレジットカード、医療ローンなどが利用できる場合があります。詳しくは、各医療機関にお問い合わせください。 |
10. まとめ
不妊治療における先進医療は、体外受精、顕微授精、胚移植など高度な技術を用いた治療法です。
それぞれに効果やリスク、費用、助成金制度があり、ご自身の状況に合った治療法を選択することが重要です。
治療を受ける際は、医療機関の選び方や治療期間、年齢制限、心構えなど、様々な注意点があります。
また、セカンドオピニオンを受けることも重要です。先進医療以外のタイミング法や人工授精などの一般不妊治療との併用も検討できます。
費用と効果のバランス、リスクへの理解、医師との相談を通して、最適な治療法を見つけてください。
治療期間中の生活や妊娠後のサポート体制についても、事前に確認しておきましょう。
何かお困りごとがありましたら、当院へお問い合わせください。
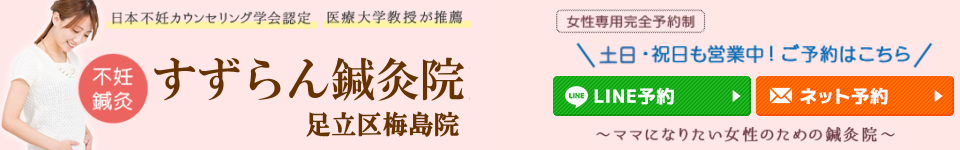
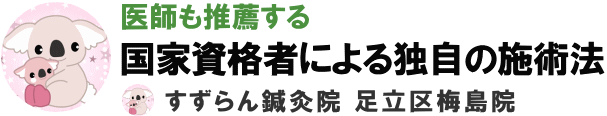













お電話ありがとうございます、
すずらん鍼灸院 足立区梅島院でございます。