
☆★☆子宝に恵まれる知恵とコツ(体外受精編)★☆★
こんにちは。すずらん鍼灸院の大島です。
前回に引き続き、胚移植(着床)について解説致します。
【ステップ1】排卵誘発
↓
【ステップ2】採卵
↓
【ステップ3】精子の採取
↓
【ステップ4】培養
↓
【ステップ5】胚移植
↓
【ステップ6】確認
胚移植では、受精し、分裂した胚盤胞を女性の体内に移植致します。採卵から胚移植までの期間は、通常、約2~3日となります。
自然妊娠による胚移植は、卵が一つしか採取されないため、当然、胚の数は一つになります。
しかし、以前に説明したように胚が一つの場合には、複数の胚移植と比べて妊娠する確率がそれだけ下がってしまいます。
そのため、多くの体外受精では、排卵誘発剤を使った方法を選択し、複数個の胚を人工的につくることになります。
培養により、つくられた複数個の胚からさらに良質の胚をいくつか選択し、細い筒状のチューブを使用して女性の体内に移植することになります。
胚移植で余った胚は、凍結してそのまま保管します。
今回の胚移植で成功しなかった場合、2度目の体外受精でその胚を使うことになります。
つまり、採卵を再度行わないで、保管した胚が使えるので、採卵の費用をそれだけ低く抑えることができます。
なお、胚移植は、複数個の胚を同時に体内に入れることになります。そのため、双子あるいは三つ子ができる可能性があります。
通常は、多くの出産をさけるため、一回の移植につき、胚は2個、もしくは3個までとなっているようです。
胚移植が終わって2~4週間経過した後、妊娠しているかの検査を行います。
妊娠判定は、ご自分で判断せず、医師に従って検査するようにします。
妊娠しているかの調査は、尿検査、あるいは血液検査で行います。
現在では、より精確に判定できる血液検査で行うことが主流になっております。
もし、ここで妊娠が確認できなかった場合には、再度、採卵から始めるか、胚移植時に余った胚を使って再度胚移植を行うことになります。
(続く)
すずらん鍼灸院
大島宏明
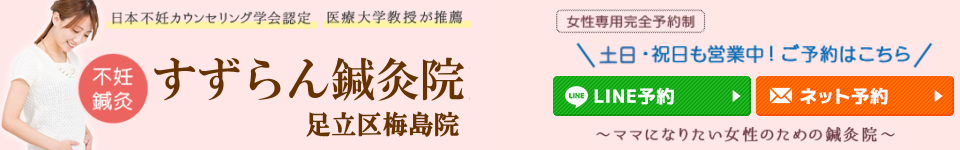
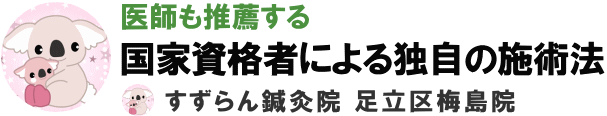






お電話ありがとうございます、
すずらん鍼灸院 足立区梅島院でございます。