不妊と東洋医学の基本的な考え方
「不妊に東洋医学ってどう関係あるの?」と感じる方も多いのではないでしょうか。
実は、西洋医学と東洋医学では体をとらえる視点が少し違っていて、それが妊活へのアプローチにもつながっていると言われています。
ここでは両者の違いや、東洋医学で大切にされる考え方、そして鍼灸が不妊改善に取り入れられる背景についてご紹介します。
西洋医学と東洋医学のアプローチの違い
西洋医学は検査によって数値化できる原因を突き止め、医学的な施術で改善を目指す方法が中心です。
一方、東洋医学は「体全体のバランス」を重視し、生活習慣や体質に合わせて整えていくことが特徴とされています。
どちらが良い悪いではなく、視点が違うからこそ両方をうまく組み合わせることが妊活にも役立つと言われています(引用元:https://touyou5.com/fertility/)。
東洋医学が大切にする「気・血・水」と妊娠の関係
東洋医学では、体を動かすエネルギーである「気」、血液の巡りを示す「血」、体内の水分バランスを意味する「水」の3つが基本とされています。
例えば、血の巡りが滞ると子宮や卵巣に十分な栄養が届きにくくなると言われていますし、気や水のバランスが乱れるとホルモンや自律神経にも影響が出ると考えられています。
これらを整えることが、妊娠しやすい体づくりにつながると考えられているのです(引用元:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsam/71/2/71_103/_article/-char/ja)。
不妊改善に鍼灸が取り入れられる背景
近年では、体外受精や人工授精とあわせて鍼灸を取り入れる方も増えてきました。
鍼灸には血流を促し、自律神経をととのえる作用があると言われており、子宮や卵巣の環境を改善する目的で選ばれるケースがあるようです。
また、西洋医学的な施術ではカバーしきれない「冷え」や「ストレス」へのアプローチができる点も注目されています(引用元:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsam/67/1/67_64/_article/-char/ja)。
#不妊改善 #東洋医学 #鍼灸 #体質改善 #妊活サポート
鍼灸による不妊改善の仕組み
鍼灸が血流や自律神経に働きかけると言われている理由
「鍼灸って本当に妊活に関係あるの?」と思う方も多いかもしれません。
実際には、鍼やお灸による刺激が体の血流や自律神経に作用する可能性があると考えられています。
たとえば、鍼を打つことで末梢の血流が良くなり、冷えや巡りの悪さが和らぐと言われています。
また、自律神経のバランスがととのうことで、ホルモン分泌や睡眠の質が改善しやすくなるとも考えられているのです(引用元:https://touyou5.com/fertility/)。
「気持ちが落ち着いたら、なんとなく体調も良くなった」という声もよく聞かれます。
こうした心と体の両面にアプローチする点が、鍼灸の特徴だとされています。
卵巣や子宮の環境をととのえるアプローチ
不妊改善の鍼灸では、特に「子宮や卵巣の環境をどう整えるか」が大切な視点になります。
血流の改善によって子宮内膜の厚さや柔らかさに影響が出る可能性があるとされ、これが着床環境をサポートする要因のひとつと考えられています(引用元:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsam/61/5/61_5_597/_pdf)。
また、卵巣への血流が良くなると、卵子の育ちにプラスになると考える専門家もいます。
ただし、効果の感じ方は人それぞれであり、数回の施術で変化が出る場合もあれば、長期的に取り組むことでじわじわ実感する方もいるようです。
鍼灸は「体質そのものを整える」というスタンスで捉えるとわかりやすいでしょう。
体外受精や人工授精と併用するケース
最近では、鍼灸を体外受精(IVF)や人工授精(AIH)と並行して行うケースも増えていると言われています。
特に移植前後に鍼灸を受けることで、リラックス効果や血流改善が期待できると考えるクリニックもあります(引用元:https://mizoguchi-shinkyu.com/fertility-acupuncture-blog/ninshin-up-shinkyu.html)。
ただし、医療のスケジュールに無理なく合わせることが大前提です。医師や鍼灸師と相談しながら、「どのタイミングで受けると自分に合うか」を決めることが安心につながります。
西洋医学と東洋医学の良さをバランスよく取り入れるスタイルは、妊活中の方にとって選択肢を広げる方法のひとつと言えるでしょう。
#不妊改善 #鍼灸 #妊活サポート #東洋医学 #体質改善
鍼灸施術の具体的なプラン
採卵前・移植前・高温期などタイミング別の施術方法
妊活に鍼灸を取り入れる場合、「いつ施術を受けるのがいいのか」がよく話題になります。
採卵前には卵巣の血流を整えて卵子の発育をサポートする目的で行われることがあるとされ、移植前には子宮内膜の状態を整えるアプローチが重視されると言われています。
また、高温期には体を温めてホルモンバランスを支える施術が行われるケースもあります(引用元:https://touyou5.com/fertility/)。
つまり、同じ「鍼灸」といっても、その時期によって狙うポイントが少しずつ変わるのです。
体のサイクルや検査のスケジュールにあわせて施術内容を調整することで、心身のリズムを無理なくサポートできると考えられています。
施術頻度(週1〜2回が目安と言われる理由)
鍼灸の頻度については、週1〜2回の施術が妊活には適しているとされることが多いです。
理由として、鍼灸の効果は一度で大きく変化するというより、積み重ねによって体質に働きかけるという考え方があるためです(引用元:https://mizoguchi-shinkyu.com/fertility-acupuncture-blog/ninshin-up-shinkyu.html)。
「続けて通うと、体が少しずつ軽くなってきた」という声も少なくありません。
もちろん個人差がありますので、体調や生活リズムに合わせて調整しながら通うのが安心です。
無理に回数を増やす必要はなく、自分に合うペースを見つけることが大切だと言えるでしょう。
医療スケジュールと両立する工夫
体外受精や人工授精を行っている方の場合、検査のスケジュールに合わせて鍼灸を取り入れるのが現実的です。
たとえば、採卵前や移植前に重点的に施術を受ける一方で、普段は週1回程度にとどめるなど、無理のない工夫がされています(引用元:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsam/61/5/61_5_597/_pdf)。
「病院と鍼灸を両立させるのは難しいのでは?」と感じる方もいますが、医師や鍼灸師と相談しながら予定を調整することで、意外とスムーズに取り入れられることも多いようです。
西洋医学と東洋医学の両方のメリットを組み合わせることで、妊活の選択肢が広がる可能性があると言われています。
#不妊改善 #鍼灸 #妊活プラン #東洋医学 #体質改善
妊娠率を高めるための生活習慣の工夫
食事・睡眠・運動のバランスをととのえる
妊活中の生活習慣は、小さな積み重ねが大きな違いにつながると言われています。
食事では、ビタミンやミネラル、タンパク質を意識してとることが推奨され、特に鉄分や葉酸を含む食品が注目されています(引用元:https://www.jsog.or.jp/modules/publication/index.php?content_id=6)。
また、睡眠も大切です。夜更かしが続くとホルモンバランスに影響が出やすいとされ、できるだけ規則正しい就寝と起床を意識するとよいでしょう。
さらに、軽めの運動を取り入れることで血流の巡りをサポートし、冷えやストレス対策にも役立つと考えられています。
ウォーキングやヨガのような体に負担の少ない運動が続けやすいとされています。
ストレスをためない工夫と夫婦の協力
妊活では、「結果が出ない焦り」がストレスの原因になることがあります。
強い緊張状態が続くと自律神経のバランスが乱れ、体に影響する可能性があるとも言われています(引用元:https://www.niph.go.jp/journal/data/73-1/202473010003.pdf)。
そこで大切なのが、夫婦で気持ちを共有することです。
「今日はちょっと疲れたから休みたい」と素直に伝えるだけでも、気持ちが和らぐケースがあります。
また、趣味の時間を持ったり、短い旅行を楽しんだりすることもリフレッシュにつながります。
鍼灸と合わせて実践したいセルフケア
東洋医学の観点では、生活習慣を整えることと鍼灸を組み合わせることで、心身のバランスをよりサポートできると考えられています。
例えば、自宅でのお灸(市販のソフト灸)やツボ押しを取り入れる方もいますし、温かい飲み物を意識して冷えを避ける工夫もよく紹介されています(引用元:https://touyou5.com/fertility/)。
セルフケアは無理なく続けられることが大切です。
日々の小さな積み重ねが体質改善につながる可能性があると言われていますので、自分に合った方法を見つけながら取り入れていくと安心です。
#妊活 #生活習慣改善 #鍼灸 #東洋医学 #不妊サポート
鍼灸を安心して取り入れるための注意点
内出血やだるさなど軽い副作用について
鍼灸は妊活のサポートとして注目されていますが、施術後に軽い副作用を感じることもあると言われています。
代表的なのは、針を刺した部位に小さな内出血ができるケースや、施術のあとに体がぽかぽかして眠気やだるさを感じるケースです(引用元:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsam/63/2/63_167/_article/-char/ja/)。
こうした反応は一時的なもので、多くの場合は数日で落ち着くとされています。ただ、不安に感じるときには、施術を受けた鍼灸師に相談して経過を見守ると安心です。
国家資格や経験豊富な鍼灸師を選ぶコツ
鍼灸を受ける際には「誰にお願いするか」がとても大切です。
日本で鍼灸施術を行うためには国家資格である「はり師」「きゅう師」の免許が必要で、資格を持つ人が施術することが基本となっています(引用元:https://www.harikyu.or.jp/)。
さらに、不妊分野に詳しい鍼灸師や、婦人科系の施術経験が多い施術者を選ぶと、安心感が高まると考えられています。
実際に相談してみて、説明が分かりやすく、自分の気持ちに寄り添ってくれるかどうかを確認するのも大切なポイントです。
医師と鍼灸師の連携・情報共有の重要性
妊活を進めるなかで、体外受精や人工授精など医療機関での検査や施術と鍼灸を並行する方も増えています。
その場合、医師と鍼灸師が情報を共有して連携をとることが理想的だと言われています(引用元:https://touyou5.com/fertility/)。
たとえば「この時期は検査があるので施術は控えた方がよい」など、両者が協力することで安全性が高まり、安心して取り組める環境が整いやすくなります。
自分だけで抱え込まず、担当の医師や鍼灸師に「両立できるスケジュールを相談したい」と伝えることが大切です。
#妊活サポート #鍼灸の副作用 #鍼灸師選び #東洋医学 #医師との連携
この記事に関する関連記事
- 不妊治療中の悩み、メンタルケアで心を守る方法|つらい感情との向き合い方
- 不妊の原因ランキング最新版|男女別の割合や特定しづらい「原因不明」の正体とは?
- 保護中: 梅島の鍼灸院で妊活と冷え性に実感できる変化を
- 鍼灸で着床率を上げる!胚移植を成功に導く子宮環境の整え方
- 保護中: 梅島で体質改善と妊活に強いすずらん鍼灸院の体験記
- 着床しにくい人の特徴と東洋医学から見た3大原因! 妊娠体質をつくる漢方・鍼灸アプローチ
- 冬の妊活、体を冷やすNG行動5選:鍼灸師が教える! 子宮を温めるための必須温活ルール
- 着床時期に控えた方がよい食べ物5選! 移植後・高温期に妊娠力を高める食事法
- 妊活に必須の栄養素5選を徹底解説! 妊娠力を高める食事とサプリの賢い選び方
- なかなか妊娠出来ない 20代へ。不安を解消し、鍼で体質改善を始めるべき理由
- 胚移植前後に最適!着床を促し妊娠へ繋げる鍼灸の活用法
- 妊活でまずやること 鍼で妊娠しやすい体質へ導く最短ルート
- 黄体機能不全でお悩みの方へ。鍼灸で体質改善を促し妊娠しやすい身体へ導く
- 体外受精と鍼灸で妊娠率を高めるには?不妊治療と東洋医学の上手な併用法
- 排卵のタイミングを整える鍼灸ケア|妊活中に知っておきたい通院のコツと効果
- 基礎体温で整える妊活と鍼灸ケア|体と心をサポートする自然な方法
- 採卵に向けた鍼灸のベストタイミング|体外受精をサポートする施術の受け方
- 妊活中のお酒と膝の重さ・違和感|体のサインを見逃さずケアする方法
- 妊活と葉酸|妊娠前から始める赤ちゃんを守る必須の栄養ガイド
- 卵子の質を改善する方法|生活習慣・食事・運動で妊娠力を高める総合アプローチ
- 妊娠しやすい鍼灸で体と心を整える|体質改善から妊活成功までの道のり
- 不妊でも妊娠率が高い方法【医療と鍼灸の併用で期待できる効果】
- 不妊鍼灸がおすすめの理由とは?妊活中に選ばれる効果と通い方のポイント
- 不妊鍼灸の頻度はどれくらい?妊娠力を高める最適ペースと続けるコツ
- 東京の不妊鍼灸|口コミ高評価&妊活に寄り添う鍼灸院の選び方ガイド
- 妊活鍼灸について|妊娠しやすい体づくりと通院前に知るべきポイント
- 東京の不妊鍼灸で妊娠力を高める!効果・口コミ・おすすめ院を徹底解説
- 卵胞発育の段階と排卵障害 – 不妊鍼灸お悩みQ&A
- 卵の補足障害における不妊症 – 不妊鍼灸お悩みQ&A
- ハムスターテストについて – 不妊鍼灸お悩みQ&A
- 精子先体反応検査について – 不妊鍼灸お悩みQ&A
- 一般不妊治療の妊娠確率について – 不妊鍼灸お悩みQ&A
- 男性不妊の割合と原因について – 不妊鍼灸お悩みQ&A
- 子宮内膜症について – 不妊鍼灸お悩みQ&A
- PCOS(多嚢胞性卵巣症候群)について – 不妊鍼灸お悩みQ&A
- 精液検査について – 不妊鍼灸お悩みQ&A
- 黄体機能不全と着床障害について – 不妊鍼灸お悩みQ&A
- 腹腔鏡検査について – 不妊鍼灸お悩みQ&A
- 受精障害の原因とメカニズムについて – 不妊鍼灸お悩みQ&A
- 一般不妊治療の妊娠確率について – 不妊鍼灸お悩みQ&A
- OHSS(卵巣過剰刺激症候群)の副作用 – 不妊鍼灸お悩みQ&A
- hMG-hCG療法について – 不妊鍼灸お悩みQ&A
- 性腺刺激ホルモン検査・卵巣性ホルモン検査 – 不妊鍼灸お悩みQ&A
- 子宮内膜検査と血中ホルモン検査について – 不妊鍼灸お悩みQ&A
- 機能性不妊と原因不明不妊について – 不妊鍼灸お悩みQ&A
- ヒューナーテストについて – 不妊鍼灸お悩みQ&A
- 子宮卵管造影について – 不妊鍼灸お悩みQ&A
- 経腟超音波診断法(検査法)について – 不妊鍼灸お悩みQ&A
- 頸管粘液検査について – 不妊鍼灸お悩みQ&A
- クロミフェン療法について – 不妊鍼灸お悩みQ&A
- タイミング指導について – 不妊鍼灸お悩みQ&A
- 西洋医学と東洋医学の併用施術について – 不妊鍼灸お悩みQ&A
- 病院・接骨院で行う鍼灸効果について – 不妊鍼灸お悩みQ&A
- 不妊専門の鍼灸院と安い鍼灸院の併用について – 不妊鍼灸お悩みQ&A
- 不妊施術の手順について – 不妊鍼灸お悩みQ&A
- 不妊の6大基本検査の必要性 – 不妊鍼灸お悩みQ&A
- 鍼の効果が効いている時間と通院期間の目安 – 不妊鍼灸お悩みQ&A
- 鍼灸で基礎体温を整える – 不妊鍼灸お悩みQ&A
- 漢方や鍼灸で基礎体温を整える – 不妊鍼灸お悩みQ&A
- 漢方薬が合わない場合の対処法 – 不妊鍼灸お悩みQ&A
- 冷え体質に鍼は有効? – 不妊鍼灸お悩みQ&A
- 鍼と整体のどちらが効くの? – 不妊鍼灸お悩みQ&A
- 鍼灸院に通う頻度 – 不妊鍼灸お悩みQ&A
- 妊娠初期・中期・後期における鍼灸施術
- 妊娠前鍼灸の勧め
- 不妊の鍼灸施術における即効性・通院期間の目安
- 上手な鍼灸院の選び方
- 鍼灸の歴史と鍼灸が有効な不妊の種類
- 東洋医療と西洋医療の不妊
- 体外受精と鍼灸の併用について
- 不妊に鍼灸はなぜ効くの?
- 不妊施術を一度も受けたことがない方へ
- 不妊鍼灸の施術について
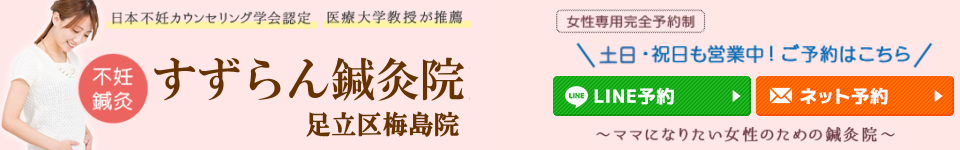
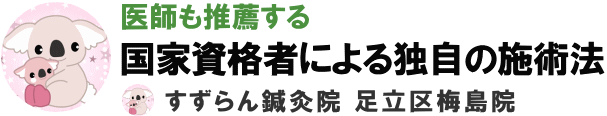











お電話ありがとうございます、
すずらん鍼灸院 足立区梅島院でございます。